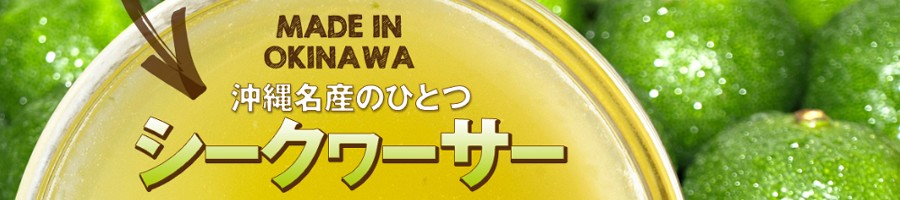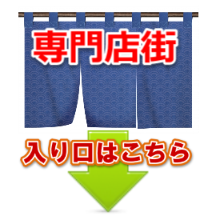シークヮーサーの栄養情報
シークヮーサーに含まれる栄養素は以下の6つです!
- ノビレチン(フラボノイド)
- 天然クエン酸
- ヘスペリジン
- 天然ビタミンC
- シネフリン
- カリウム

ノビレチン
柑橘類の果皮等に多く含まれる有機化合物で、フラボンを骨格に持つポリメトキシフラボノイド(O-メチル化フラボノイド)の一種である。
主に柑橘類に多く含まれており、特にポンカン、シークヮーサー、橘等に多く含まれている。
可食部分である果実小胞自体にはあまり含まれておらず、果皮部分であるフラベド(外果皮)、アルベド(中果皮)に特に多く含有している。
in vitroや動物実験で、抗炎症作用や腫瘍の浸潤、拡散、転移を防ぐ作用、皮膚炎抑制作用、肝炎抑制作用等が示されている。
また、軟骨の分解を抑制する効果も報告されている。
また、培養海馬細胞においてAMPA型グルタミン酸受容体を活性化し、ニューロンの長期増強を促進することが示されている。
以上の効能からダイエットサポート・美白ケア・アンチエイジングなどが期待できます。
天然クエン酸
クエン酸(クエンさん、citric acid)は、示性式 C(OH)(CH2COOH)2COOH で、柑橘類などに含まれる有機化合物で、ヒドロキシ酸のひとつである。
柑橘類の酸味の原因はクエン酸の味に因るものが多い。また、梅干しにも多量に含まれている。
5km走での実験から、運動成績を有意に向上させることが報告されたが、その後否定されている。
このほか、高強度運動や600m走でも運動成績には影響がないことが示されている。
運動後はブドウ糖を単体でとるよりも、そこにクエン酸を加えた方が、グリコーゲンを多く貯蔵できる。
日本薬局方収載品であり、薬局などでも市販されている。クエン酸の塩はカルシウムイオンとキレート結合するので、かつては検査用血液サンプルの抗凝固薬などとしても利用された。
現在でも成分献血時にクエン酸ナトリウムとともに抗凝固薬として使用される。
クエン酸ナトリウム・クエン酸カリウム合剤(商品名ウラリットR配合錠)は尿をアルカリ化させ尿酸の排泄を促進することから痛風に代表される高尿酸血症の治療薬として処方され、尿路結石や代謝性アシドーシスの治療にも使用される。
食品添加物でもあり、清涼飲料水を始め各種の加工食品に添加される。
炭酸カルシウムを容易に溶かすことから電気ポットや加湿器内部に溜まった水垢の洗浄にも用いられる。
肥料の成分がクエン酸の2%水溶液に溶解する性質を「く溶性」という言葉で表すが、これは植物の根が分泌する根酸には溶けにくいがもう少し強い酸には溶けることを意味し、徐々に溶け出してゆっくり吸収されることを示す。
以上の効能から疲れ回復・美肌効果などが期待できます。
ヘスペリジン
ヘスペリジン (Hesperidin) は、温州みかんやはっさく、ダイダイなどの果皮および薄皮に多く含まれるフラバノン配糖体(フラボノイド)である。
ポリフェノールの一種。陳皮の主成分。ビタミンPと呼ばれるビタミン様物質の一部。ギリシア神話のニュンペー・ヘスペリデスから名付けられた。
ヘスペリジンは植物の防御に関与していると考えられている。In vitroの実験では抗酸化物質として働く。
様々な薬理作用に関する報告がこれまでになされている。ヘスペリジンはラットにおいて、コレステロールや血圧を低下させる。
マウスを用いた実験で、大用量のヘスペリジンは骨密度の低下を抑制するほか[4]、敗血症に対する保護効果が示されている。
ヘスペリジンは抗炎症作用を示す。
また、ヘスペリジンは抗不安作用を示し、これはオピオイド受容体もしくはアデノシン受容体を介して効果を示している可能性が考えられている。
アグルコン型の活性についてもIn vitroで研究されており、in vitroモデルで血液脳関門を通過できることが示されている。
その他、毛細血管を強化し、血管透過性を抑える働きや、抗アレルギー作用、血圧降下作用、血清脂質改善作用、抗酸化作用、発がん抑制作用等を示す。
以上の効能から花粉症緩和などが期待できます。
天然ビタミンC
ビタミンC (vitamin C, VC) は、水溶性ビタミンの1種。化学的には L-アスコルビン酸をさす。生体の活動においてさまざまな局面で重要な役割を果たしている。
食品に含まれるほか、ビタミンCを摂取するための補助食品もよく利用されている。WHO必須医薬品モデル・リスト収録品。
壊血病の予防・治療に用いられる。鉄分・カルシウムなどミネラルの吸収を促進する効果があるが、摂取しすぎると鉄過剰症の原因になることがある。風邪を予防することはできない。
ビタミンCは、コラーゲンの合成に深く関与している。
プロリン・リジン残基を含めた形でコラーゲンのタンパク質が合成され、タンパク質鎖が形成された後で酸化酵素によりプロリン・リジン残基がそれぞれヒドロキシ化(水酸化)を受けてヒドロキシプロリン・ヒドロキシリジン残基に変化し、これらは水素結合によってタンパク質鎖同士を結び、コラーゲンの3重螺旋構造を保つ働きがある。
またこの反応の際にはビタミンCを必要とするため、ビタミンCを欠いた食事を続けていると正常なコラーゲン合成ができなくなり、壊血病を引き起こすものである。
ビタミンCは、水溶性で強い還元能力を有し、スーパーオキシド(O2-)、ヒドロキシラジカル(・OH)、過酸化水素(H2O2)などの活性酸素類を消去する。
ビタミンCの過酸化水素の消去は、グルタチオン-アスコルビン酸回路によって行われる。
この回路に代表されるように、ビタミンCがデヒドロアスコルビン酸に酸化されても各種酵素によりビタミンC(アスコルビン酸)に還元・再生されて触媒的に機能する。
ビタミンCは、ビタミンEの再生機能がある。活性酸素等のフリーラジカルはDNAやタンパク質を攻撃し、また、脂質を連鎖的に酸化させる。
ビタミンEは、脂質中のフリーラジカルを消失させることにより自らがビタミンEラジカルとなり、フリーラジカルによる脂質の連鎖的酸化を阻止する。
発生したビタミンEラジカルは、ビタミンCによりビタミンEに再生される。
その他のビタミンCの機能としては、生体異物を代謝するシトクロムP450の活性化、チロシンからノルアドレナリンへの代謝(ドーパミンヒドロキシラーゼ)、消化器官中で鉄イオンを2価に保つことによる鉄の吸収の促進、脂肪酸の分解に関与するカルニチンがリジンから生合成される過程のヒドロキシ酵素の補酵素としての参画、コレステロールをヒドロキシ化し7α-ヒドロキシコレステロールを経た胆汁酸の合成等の様々な反応に関与している。
以上の効能から健康維持・美容効果などが期待できます。
カリウム
カリウム(ドイツ語: Kalium [?ka?li?m]、新ラテン語: kalium)は原子番号 19 の元素で、元素記号は K である。原子量は 39.10。
アルカリ金属に属す典型元素である。医学・薬学や栄養学などの分野では英語のポタシウム (Potassium [po??tasi?m]) が使われることもある。
生物にとっての必須元素であり、神経伝達で重要な役割を果たす。
人体では8番目もしくは9番目に多く含まれる。植物の生育にも欠かせないため、肥料3要素の一つに数えられる。
一日の所要量は約 0.8?1.6 g とされる。
2010年5月の厚生労働省「日本人の食事摂取基準」で目安量は男性 2,500 mg/日、女性 2,000 mg/日と勧告されているが、アメリカ、イギリスでは生活習慣病予防の観点から、男女ともに目安量4,700 mg/日、推奨量3,500mg/日としている。
植物、動物の細胞には豊富に含まれており、通常の食事で生命を維持するために必要なカリウムは十分に賄われる。そのため、カリウムの血中濃度の低下による低カリウム血症(カリウム欠乏症)の顕著な徴候や症状が健康な人に現れることは希である。
カリウムの豊富な食品として、パセリや乾燥させたアンズ、粉ミルク、チョコレート、木の実(特にアーモンドとピスタチオ)、ジャガイモ、タケノコ、バナナ、アボカド、ダイズ、糠などに特に多く含まれるが、大部分の果実、野菜、肉、魚において人体に十分な量が含まれている。
なお、カリウムの最適摂取量に関しては、いくつかの議論が存在する。例えば、アメリカ医学研究所は2004年にカリウムの食事摂取量基準(英語版)を一日あたり4,000 mg (100 mEq) と指定したが、アメリカ人の平均的カリウム摂取量はその半分程度しかないため、大部分が摂取不足であることになる。同様に欧州連合、特にドイツとイタリアにおいても、カリウムは一般的に摂取不足の傾向にあると考えられている。
高血圧についての疫学的研究および動物実験の結果、カリウム含有量の高い食品の摂取によって高血圧のリスクを低減できることが示され、高血圧を原因としない脳卒中についても低減されると考えられている。
イタリアの研究者によるメタアナリシスに基づいてた報告(2011年)によると、一日に 1.46 g 以上カリウムを摂取すると脳卒中のリスクが21%低減するとされる。
また、ラットを用いた研究において、カリウムの欠乏はチアミン(ビタミンB1)の摂取不足と複合すると心臓病を誘発することが示された。
以上の効能から高血圧予防などが期待できます。
シネフリン
シネフリン (synephrine) またはp-シネフリンは、数種の動植物が生成するアルカロイドの一つ。
ミカン科ウンシュウミカン、ナツミカン、ダイダイ、ゴシュユの果実に含まれている酸味成分。
気管支を拡張させ、のどの風邪にも効果があるとも言われる。脂肪分解酵素のリパーゼを活性化するとも言われる。
脂肪の代謝を促進するとも言われる。食欲を抑える働きもあるとも言われる。
以上の効能からダイエット効果などが期待できます。
(wikipediaより抜粋)
▼ 通常価格2,600円がワクワク定期コースで1本あたり初回975円!(税抜) ▼